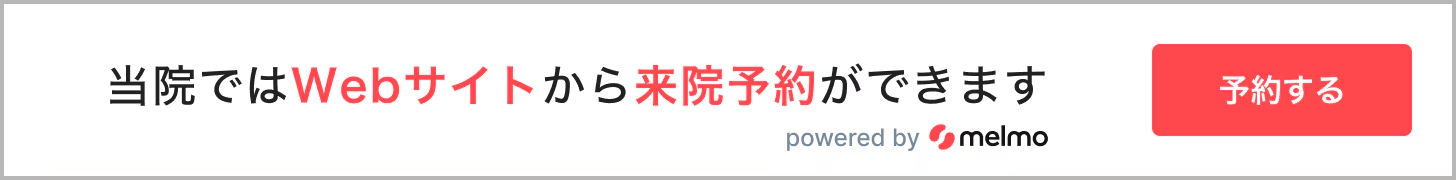乳がんのあとにリンパ浮腫になる可能性があると知り、不安になってはいないでしょうか。
乳がん治療後は、手術や放射線、抗がん剤の影響でリンパ液の流れが悪くなり、リンパ浮腫を発症することがあります。リンパ浮腫は水分による一般的なむくみと違い、放っておくと進行するうえ、合併症が心配される疾患です。
本記事では、乳がんの治療後にリンパ浮腫が起こる理由や予防法を解説します。漠然と不安を募らせるだけでなく、正しい情報をもとにケアをして、リンパ浮腫を予防しましょう。
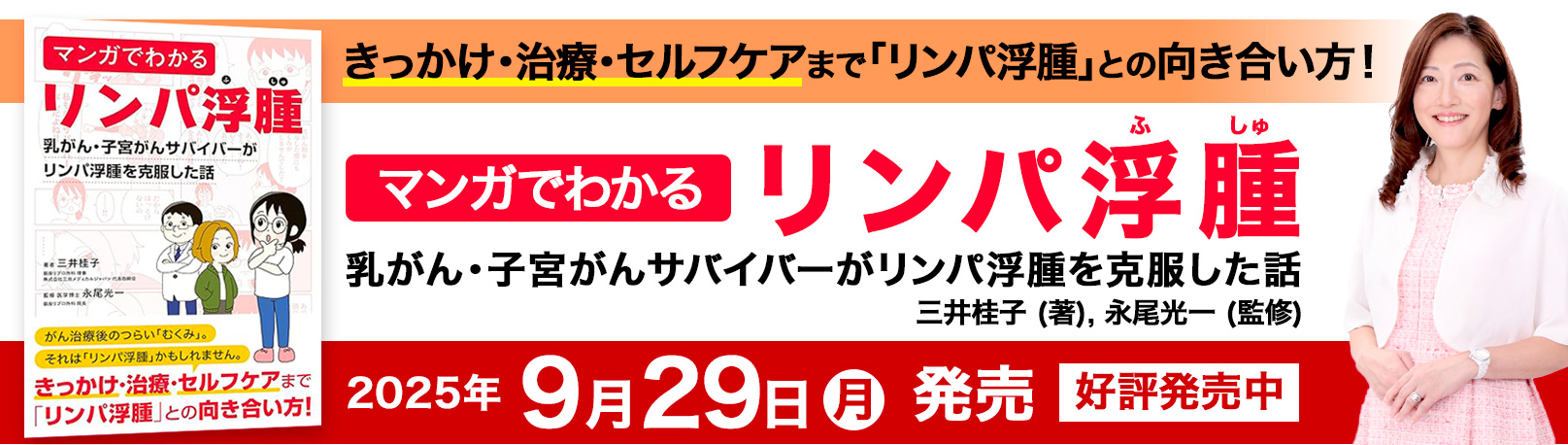
乳がん治療後にリンパ浮腫が起こる理由
乳がんの治療後に腕にリンパ浮腫が生じやすい理由は、以下のとおりです。
・リンパ管やリンパ節が損傷する
・手術でリンパ節が取り除かれる
・センチネルリンパ節生検を受けた
・抗がん剤による薬剤性浮腫から移行する
リンパ浮腫は、リンパ液の流れが悪くなり、体がむくんでしまう病気です。乳がん治療後にリンパ浮腫が起こる具体的な理由について詳しく解説します。
リンパ管やリンパ節が損傷する
乳がんの進行や転移を防ぐための手術や放射線治療でリンパ管やリンパ節が損傷し、リンパ浮腫が起こることがあります。
リンパ管の役割の1つは、体内の老廃物や余分な水分を回収し、リンパ液として血管へと戻すことです。リンパ節はリンパ管の途中に存在し、免疫に関する大切な役目を担っています。
手術や放射線治療によってリンパ管やリンパ節が傷つくと、リンパ液がスムーズに流れず、損傷した部位の周辺に溜まりやすくなります。乳がん手術においてリンパ管系の損傷は避けられない場合もあるため、治療後は正しい情報にもとづく適切なケアに取り組みましょう。
手術でリンパ節が取り除かれる
乳がんの手術でリンパ節を切除することも、リンパ浮腫が起こる原因です。
リンパ液に侵入したがん細胞は、関所のような役割のリンパ節でせき止められます。しかし、一部のがん細胞はリンパ節内で増殖したり、通過して全身に転移したりします。わきの下のリンパ節切除は、乳がんの進行を防ぐために選ばれる治療法の1つです。
リンパ液をろ過しながら体の各部位へ送り出す役目のリンパ節が手術で取り除かれると、体内の循環が妨げられます。流れにくくなったリンパ液が停滞した結果、腕や手のむくみが発生します。
乳がんの手術でリンパ節を除去した患者さんは、治療終了後も継続したケアが必要です。
センチネルリンパ節生検を受けた
乳がんの転移を調べるためにセンチネルリンパ節生検を受けた方も、リンパ浮腫発症の可能性があります。
センチネルリンパ節生検とは、乳がんのがん細胞が初めに到達するリンパ節(センチネルリンパ節)を見つけて摘出し、転移を調べる方法です。センチネルリンパ節は、がんの周りに放射線を発する物質や色素を注射して発見します。
センチネルリンパ節にがん細胞がなければ、ほかのリンパ節に転移している可能性は低いと判断されます。センチネルリンパ節生検が実施されるようになったことで、検査のためにわきの下のリンパ節を切除するケースが減りました。
しかし、検査時のわずかなリンパ節の損傷によりリンパ管系の機能が低下し、リンパ浮腫を発症する患者さんが見受けられます。
リンパ節を切除していなくても、該当の検査を受けた方はセンチネルリンパ節を摘出した側の腕の状態に注意しておくことが必要です。
抗がん剤による薬剤性浮腫から移行する
リンパ浮腫は、抗がん剤による薬剤性浮腫から移行して発症する場合もあります。乳がん治療に使われるタキサン系抗がん剤は、リンパ浮腫を発症させる可能性があるといわれています。
参考:タキサン系薬剤は続発性リンパ浮腫発症の危険因子か?|日本リンパ浮腫学会
抗がん剤使用中の副作用としてよく見られるむくみは、治療終了にともなって改善していくケースがほとんどです。抗がん剤投与中に全身にあったむくみが、終了後に乳がん発症部位の近くにだけ残った場合は、リンパ浮腫を起こしている可能性があります。
抗がん剤を用いた治療のなかでむくみが生じた方は、こまやかな経過のチェックが欠かせないことを認識しておきましょう。
乳がん治療後のリンパ浮腫の特徴
乳がん治療後のリンパ浮腫の特徴を紹介します。むくみが起こりやすい部位や初期症状を把握しておくことで、早期発見・受診が可能になります。
乳がんを発症した部位の近くに違和感があった場合は早めに医師に相談し、適切な治療を受けましょう。
リンパ浮腫が起こりやすい場所
がんのあとに発症するリンパ浮腫は、治療の影響を受けたリンパ節やリンパ管の近くに限定して起こります。乳がん治療後の患者さんの多くは、次のような場所に発症します。
・治療を受けた胸側の腕
・治療を受けた胸側のわきの下
・胸
・背中
乳がんの治療が終わったら、自分がリンパ浮腫を発症する可能性がある場所を把握し、日頃からチェックすることが大切です。
見た目だけでなく、皮膚の張りや色・つまみにくさに変化がないかを確認する習慣をつけると良いでしょう。少なくとも月に1回は、同じ時間に腕の決まった部分の太さを測ることもおすすめです。
自身の体を普段から注意深く観察し、違和感があればすぐに担当医へ相談してください。
初期症状
乳がん治療後のリンパ浮腫における初期症状は、以下のとおりです。
・腕が重だるい
・指輪や腕時計の痕が残るようになった
・腕の皮膚につっぱり感がある
・二の腕や手の甲がむくむ
乳がん治療直後は肩や胸が腫れることがあり、だるさやむくみがリンパ浮腫の症状だと早期に気づけない可能性があります。ただし、リンパ浮腫は早期発見・治療が進行防止のカギなので、違和感を見逃さないことが大切です。
リンパ浮腫のリスクに常におびえる必要はありません。不安なときは一人で抱え込まず、医師や専門家に相談することをおすすめします。
乳がん治療後のリンパ浮腫予防のために
リンパ浮腫予防のために、乳がん治療後は以下のポイントに気をつけて毎日を過ごしましょう。
・リンパ節を取った側の腕に傷をつけない
・リンパ節を取った側の腕を圧迫しない
・無理をせず適度な休憩を心がける
リンパ浮腫は、一度発症すると完治が難しいため、予防が非常に重要です。日常生活での少しの工夫やケアによって、リンパ浮腫発症のリスクを大幅に軽減できる可能性があります。
リンパ節を取った側の腕に傷をつけない
リンパ浮腫予防のために、リンパ節を取った側の腕に傷をつけないように心がけましょう。
乳がんの手術でリンパ節を取った側の腕は、リンパ液の流れが悪くなっています。小さくても傷があると、血液の循環量が増えてリンパ浮腫発症のリスクが高まると同時に、菌が入り込み感染症の原因となる恐れがあります。
日常生活のなかで、傷を防ぐ以下のような工夫をしましょう。
・リンパ節を取ったほうの腕に美容鍼は避ける
・採血・注射は反対側の腕で行なってもらう
・庭仕事や料理をするときは手袋をつける
・外出するときは長袖を着る
乳がん治療をしたと外見ではわかりにくい場合もあるので、初めての病院で健康診断や予防接種を受ける際は、自己申告する勇気を持つことも大切です。
リンパ節を取った側の腕を圧迫しない
乳がん治療後のリンパ浮腫を防ぐには、リンパ節を取った側の腕の血流やリンパ液の流れを妨げるような圧迫を避けてください。
日常生活で腕を圧迫する危険は、以下のような場面に潜んでいます。
・衣服の締め付け
・アクセサリーや腕時計の着用
・血圧測定
・荷物運び
・就寝時の姿勢
リンパ節を取った側の腕に指輪や腕時計を装着することは、できる限り避けましょう。荷物を持つときも、圧力が片側の腕に偏らないようにカートを使用したり、家族に頼ったりといった工夫が大切です。
就寝時は腕が体の下敷きにならないように注意し、枕やクッションなどで少し高く上げることをおすすめします。
無理をせず適度な休憩を心がける
乳がん治療後の生活では、無理をせず適度な休憩を心がけ、リンパ浮腫を予防しましょう。
デスクワークや家事などで長時間同じ姿勢を続けると、リンパ液が溜まりやすくなります。こまめに休憩し、軽くストレッチすると、リンパ液の流れを促進できます。
休憩しても疲れが残るような重労働をしなくてすむように、周囲の人や家族に理解してもらっておくことも重要です。
生活のなかで、意識的にリンパ液の流れを良くする習慣を取り入れることで、リンパ浮腫のリスクを軽減できる可能性があります。
乳がん治療後のリンパ浮腫を放っておくと?
乳がん治療後のリンパ浮腫は、初期の段階では軽いむくみ程度ですが、放置により症状が悪化し、日常生活に支障をきたすでしょう。重症化すると治療が難しく、合併症を引き起こすリスクもあります。
リンパ浮腫の早期発見・治療が重要な理由を詳しく説明します。
日常生活に影響を及ぼす
日常生活に影響が及ぶ可能性があることは、リンパ浮腫を放置した場合のリスクの1つです。
重症化した乳がん治療後のリンパ浮腫の症状は、以下のとおりです。
変性した脂肪が皮下に沈着して腕が太くなる
皮膚が硬くなる
痛みが出現する
腕が太く・皮膚が硬くなると、関節の曲げ伸ばしに支障をきたすでしょう。物を持つことや細かい作業が難しくなる可能性もあります。
痛みが強くなると、思ったように仕事・家事が行えず、精神的に落ち込んでしまうかもしれません。日常生活に支障をきたす前に、適切なケアを行なってリンパ浮腫の悪化を防ぎましょう。
治療が難しくなる
乳がん後のリンパ浮腫は、初期の段階で適切なケアをすれば症状を軽減できる一方で、放置により悪化が進み、治療が難しくなります。
国際リンパ学会では、下記のようにリンパ浮腫の程度を分類しています。
| 0期 | リンパ液輸送が障害されているが、浮腫が明らかでない潜在性または無症候性の病態。 |
| Ⅰ期 | 比較的蛋白成分が多い組織間液が貯留しているが、まだ初期であり、四肢を挙げることにより軽減する。 |
| Ⅱ期 | 四肢の挙上だけではほとんど組織の腫脤が改善しなくなり、圧痕がはっきりする。 |
| Ⅱ期後半 | 組織の線維化がみられ、圧痕がみられなくなる。 |
| Ⅲ期 | 圧痕がみられないリンパ液うっ滞性象皮病のほか、アカントーシス(表皮肥厚)、脂肪沈着などの皮膚変化が見られるようになる。 |
Ⅰ期は「可逆期」ともいわれ、むくみがまだもとに戻りますが、「非可逆期」であるⅡ期になると症状が慢性化し、セルフケアでは改善困難です。
変性したリンパ管や皮下組織は、完全に健康な状態には戻りません。症状が軽いうちに専門医の診察を受け、適切な治療を開始することが大切です。
合併症が起こりやすい
合併症が起こりやすくなることも、乳がん治療後のリンパ浮腫を放置した際のリスクの1つです。放置されたリンパ浮腫は、以下のような症状を引き起こす恐れがあります。
| 象皮症(ぞうひしょう) | 皮膚が象のように分厚くなる |
| リンパのう胞 | 皮膚に1~2mmほどの袋のようなイボができる |
| リンパ漏 | リンパ液が皮膚から漏れ出す |
| 蜂窩織炎(ほうかしきえん) | 免疫機能が低下してけがや虫刺されから細菌に感染する |
特に注意が必要なリンパ浮腫の合併症が、蜂窩織炎です。蜂窩織炎になると、手足に赤い斑点が広がって痛み・腫れなどが見られ、リンパ管の炎症がリンパ浮腫をさらに悪化させる原因となります。40℃近くまで発熱し、ときには命にもかかわります。
重篤な合併症を避けるためにも、「リンパ浮腫かもしれない」と思ったら早期受診が不可欠です。
乳がん後のリンパ浮腫の治療法

乳がんのあと、腕に発症したリンパ浮腫には症状に応じて「保存的治療」と「外科的治療(手術)」を組み合わせた治療をします。
リンパ浮腫は、一度発症すると完治が難しい疾患です。リンパ管の機能が残っている元気な状態のほうが、治療がスムーズに行える可能性があります。
症状が進行するほど治療もケアも複雑になるため、早期発見・受診が重要です。
保存的治療
乳がん後のリンパ浮腫では、傷や大きな身体的負担をともなわない、以下のような保存的治療が用いられます。
・スキンケア
・用手的リンパドレナージ(手で行う医療的マッサージ)
・弾性包帯や弾性スリーブなどによる圧迫療法
・圧迫した状態で行う運動療法
保存的治療の目的は、感染症の防止やむくみの原因となっているリンパ液をリンパ管に戻すことです。1つの手法だけでなく複数を組み合わせることで、より高い治療効果が期待できます。
保存的治療は、生活のなかで自分で行う必要もあります。信頼できる専門家のもと、長い目で治療に取り組みましょう。
外科的治療(手術)
外科的治療(手術)も、乳がん治療後に発症したリンパ浮腫に用いられ、大きく以下の2つに分類されます。
・機能再建手術
・減量手術
機能再建手術とは、新しいリンパ管の流れを作ってリンパ液の運搬機能を回復させる手術です。リンパ管の機能が残っているほうが治療効果を得やすいため、症状が軽い早期の段階での手術をおすすめします。
機能再建手術のうち、リンパ管と皮下静脈をつなぐリンパ管静脈吻合術(LVA)は、局所麻酔で行え、日帰りで手術可能な方法です。体内の健康なリンパ管やリンパ節を病気の部分に移植する手術の場合は、入院が必要です。
減量手術は沈着した組織を除去する術式で、症状の進行した患者さんは機能再建手術との併用を勧められることもあります。
手術後も保存的治療を継続することで、リンパ浮腫のある腕を良い状態に保てます。
乳がん治療後のリンパ浮腫でお悩みなら当院へ
乳がん治療後のリンパ浮腫のお悩みは、当院へご相談ください。
当院では、リンパ浮腫に対する専門的な診断・治療を行なっています。完全予約制のため、リンパ浮腫についてのお悩みをゆっくりと専門医にご相談いただけます。
スリーブについてのご相談や、日常生活の注意点について指導やサポートが受けたい方は、院内に設けている「リンパルーム」のご利用も可能です。
「乳がん治療後のリンパ浮腫が心配だけど相談場所がない」という方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・ご予約はこちら
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F
この記事の執筆医師

永尾 光一 先生
一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長
医療法人社団マイクロ会 理事長
銀座リプロ外科 院長
昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。形成外科診療科部長を経験する(基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。
診療・手術一覧
この記事を見た人はこんな記事も見ています
リンパ浮腫の合併症には、蕁麻疹のように赤い斑点が出る蜂窩織炎があります。「じきに治るだろう」と受診しないことは非常に危険です。 一般的に、蕁麻疹は時間の経過とともに発疹が消失しますが、蜂窩織炎は放置す…
続きを読むがんの手術後、しばらく経った頃から「むくみが取れない」と気になっていませんか。 がん治療部位の近くのむくみは、リンパ浮腫の可能性があります。治療したがんの種類別で発症率が異なるため、自身にリンパ浮腫が…
続きを読む丁寧にケアしていたはずのリンパ浮腫がある部位に赤みが出現し、どのように対処したら良いのか困っていませんか。 むくんだ腕や脚に赤み・熱感がある場合は、蜂窩織炎を疑い、すみやかに受診することが推奨されます…
続きを読むがん治療をした部位にむくみが続き、「リンパ浮腫かもしれない」と不安になっていませんか。 リンパ浮腫は、リンパ液の流れが障害された部位に起こる、むくみや重だるさを特徴とした病気です。一度発症すると自然に…
続きを読むお問い合わせ・ご予約はこちら
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F


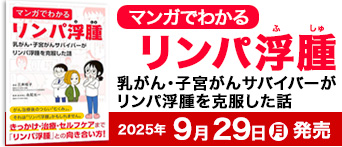
 初診のご予約
初診のご予約 再診のご予約
再診のご予約