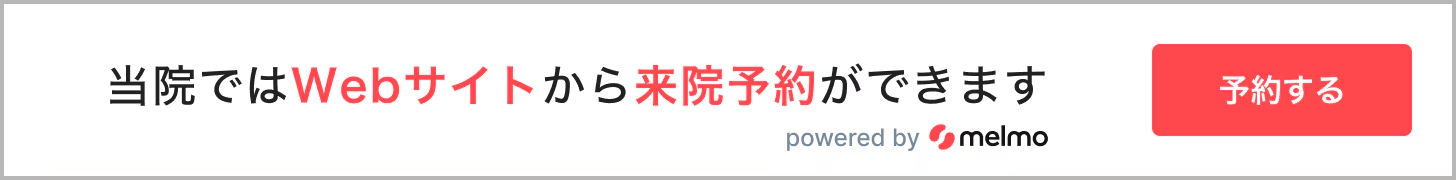近年、血管の水分が出入りするメカニズムに、グリコカリックスという薄い膜のような構造体が関わっていることがわかってきました。
「血管における水分の出入りは、アルブミンによる浸透圧で調整されている」といった、これまでの見解に一石を投じる研究結果が次々と報告されています。
本記事では、注目を集めているグリコカリックスに関する基礎知識や、明らかになってきている機能について詳しく解説します。
リンパ管にも存在することが明らかになったグリコカリックスとむくみの関連について、新しい知見も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
血管から水分が漏れるメカニズムの常識が変わる?
近年、水分が血管を出入りするメカニズムについて新たな知見が報告されました。
通常、血管と組織の間では、常に水分のやり取りが行われています。体内の水分は、血管から組織への供給やリンパ管による回収が行われ、バランスが保たれています。
何らかの原因でバランスが崩れてしまい、組織内の水分量が過剰になった状態が「むくみ」です。
これまでの定説|アルブミンによる浸透圧説
今まで長い間、血管から水分が出ていく仕組みは、アルブミンによる浸透圧が引き起こす現象だと考えられてきました。
アルブミンとは、血液中に存在するタンパク質です。タンパク質には水分を引きつける働きがあります。
アルブミンが膠質浸透圧を発生させ、血管の外に水分が過剰に漏れ出すことを防いでいるといわれていました。膠質浸透圧とは、血管内に水分を引きつける力です。
血圧で血管から水分が押し出されても、アルブミンによる膠質浸透圧で再吸収され、バランスが取れているといった認識でした。
新説!グリコカリックスが体液の漏出を調整
近年、グリコカリックスという構造体が、血管から水分が漏れ出る仕組みを調整していることが明らかになってきました。血管内の水分は外向きにのみ移動し、漏れ出たあとはリンパ管ですべて回収されてから静脈に戻るといった新しい見解も注目されています。
むくみや炎症のメカニズムを解明することは、患者さんの悩みを解消するうえで非常に重要です。グリコカリックスに関する研究が、むくみの治療や予防につながる可能性が期待されています。
今注目されているグリコカリックスとは
グリコカリックスとは、血管の内側を覆っている、糖とタンパク質でできたゼリー状の構造体です。厚さは約0.02〜1μm(1,000分の1mm程度)で非常に薄く、通常の顕微鏡では見えません。
体のどこに存在するのか・どのような場面での活用が期待されているのかを知り、グリコカリックスについて理解を深めましょう。
どこに存在する?
グリコカリックスは、基本的に人間のすべての細胞に存在します。しかし、一般的に「グリコカリックス」というと、血管の内側にあるものを指すことが多いでしょう。
血管の内側、専門的な言葉では血管内皮にあるグリコカリックスは、血液と組織の間で、体全体の水分調整を支える存在です。
最近では、リンパ管や消化管・肺胞などでも大切な働きがあることが知られてきており、全身の健康維持に関わっている可能性を示しています。
医療分野での活用が期待されている
グリコカリックスは、医療現場で注目を集めており、治療への活用が期待されています。
炎症や糖尿病、手術・外傷などでのグリコカリックスの破壊は、血管から水分が過剰に漏れ出すことによるむくみやショックの原因です。特に救急医療の現場において、敗血症や人工呼吸管理中など、重篤な状態のときに壊れると、腎不全や肺水腫が起こりかねません。
グリコカリックスの保護・修復によりショックを防ぐ治療法の研究が進められています。
動脈硬化はグリコカリックスの破壊から始まるといわれています。グリコカリックスを保護して動脈硬化の予防につなげられれば、生活習慣病の患者さんを大きく減らせるでしょう。
グリコカリックスの変化を病気のサイン(バイオマーカー)として利用することも期待されています。
血管内グリコカリックスの役割
血管内グリコカリックスにおける、現在明らかになっている役割は以下のとおりです。
- 血管内の細胞を保護して健康に保つ
- 血管透過性を調節する
- 炎症反応をコントロールする
- 血栓形成を防ぐ
私たちの体の健康を維持するために欠かせないグリコカリックスの機能について、詳しく解説します。
血管内の細胞を保護して健康に保つ
血管の細胞の保護は、グリコカリックスの大切な役割の1つです。
グリコカリックスは、血管内皮細胞の表面をコーティングするように存在し、物理的なバリアとして働いています。具体的には、血流中の摩擦や有害物質から内皮細胞を守り、血管の劣化を防いでいます。
特に、血流の圧力が比較的高い動脈や、血液成分との接触が頻繁に起こる毛細血管は、内皮細胞が傷つきやすい環境です。グリコカリックスは、ストレスから細胞を守り、血管の老化や損傷を抑える働きをしています。
血管透過性を調節する
グリコカリックスは、血液中の水分やタンパク質が血管の外に漏れ出すことを防ぐ、フィルターのような役割も持っています。
グリコカリックスを構成する要素の1つであるグリコサミノグリカンは、マイナスイオンを帯びていることが特徴です。同様にマイナスイオンを帯びているアルブミンが血管から出ていくことを防ぎ、膠質浸透圧の働きが弱まらないようにコントロールしています。
マイナスイオンを持っている物質同士は、互いに反発しあう性質があります。2つの磁石のN極同士を近づけると、反発して離れようとすることをイメージするとわかりやすいでしょう。
グリコカリックスが正常に機能していれば、必要な量の水分やタンパク質だけを通し、不要な漏出が回避可能です。しかし、何らかの原因によってグリコカリックスが破壊されると、バランスが崩れ、体液が血管の外へ異常に漏れ出してしまいます。
血管から水分やアルブミンなどの成分が必要以上に漏れ出ることで、むくみや炎症が生じます。
炎症反応をコントロールする
炎症時に、内皮細胞と白血球が過剰に接着しないように調整することもグリコカリックスの役割です。
炎症が起きた際、白血球のような免疫細胞が血管内を通って患部に向かいます。免疫細胞が内皮にくっつくと、接した部分から炎症を促す物質が放出され、血管の透過性が高まります。
結果として、周囲に水分や免疫細胞が集まりすぎ、組織が腫れたり慢性的なダメージを受けたりするでしょう。
グリコカリックスは、白血球が内皮にくっつくことを防ぐ作用を持ち、必要以上の炎症反応が起こらないように抑えています。グリコカリックスが傷ついていると、免疫細胞が内皮細胞に接触しやすくなり、炎症の慢性化につながる恐れがあります。
血栓形成を防ぐ
血栓形成の抑制も、グリコカリックスの機能です。
血液が固まって血のかたまりができると、脳梗塞や心筋梗塞などの命に関わる疾患につながります。グリコカリックスの役割の1つは、血小板や血液凝固因子が血管の内皮に接触することを防ぎ、血液をサラサラに保つことです。
健康なグリコカリックスは、血液の流れをスムーズに保つ潤滑剤のような働きをし、血栓形成を抑えます。高血糖・炎症・酸化ストレスなどによってグリコカリックスが破壊されると、血小板が内皮に付着しやすくなり、血栓ができるリスクが高まるでしょう。
リンパ管でもグリコカリックスが発見された
これまで、グリコカリックスは主に血管内に存在する構造体として知られてきました。しかし、近年の研究によって、リンパ管の内側にも存在することが明らかになっています。
リンパ管も血管と同じように、グリコカリックスによる精密な生理的機能を持っている可能性が示唆されています。
リンパ管のグリコカリックスの働き
血液からしみ出した水分の回収は、リンパ管の役割です。グリコカリックスが血管内で水分の移動をコントロールしているように、リンパ管内でも同様の働きをしているのではないかという研究が進められています。
血管のみならずリンパ管におけるグリコカリックスも、以下のような働きを担っていることは十分に考えられます。
- 血管や組織からの水分・タンパク質の吸収量調整
- 炎症の制御
- 免疫細胞の移動の調整
- 病原体や異物の進入防止
リンパ管は、免疫細胞の通り道です。内皮細胞に物質がくっつくことを防ぐグリコカリックスの作用は、免疫細胞の通過にも関わっていると予測され、今後の研究で明らかになっていくでしょう。
グリコカリックスとむくみの関係
むくみの発症や悪化にも、グリコカリックスが関係していると考えられています。
- グリコカリックスは炎症によって壊れやすい
- グリコカリックスが壊れるとむくみやすくなる
発症のメカニズムがわかることで、新たな予防法・治療法の開発につながる可能性が期待されます。
グリコカリックスは炎症によって壊れやすい
グリコカリックスは、炎症や酸化ストレス、外科的ダメージ、感染などによって簡単に壊れてしまう構造体です。以下のような病気や症状は、グリコカリックスを壊すリスクがあります。
- 細菌感染により全身に症状が出る敗血症
- 点滴の影響で体液が増えすぎたケース
- 多発外傷
- 重度のやけど
- 高血糖状態
- 糖尿病
- 高コレステロール血症
壊れたグリコカリックスは血管やリンパ管から剥がれ落ち、再生は困難です。グリコカリックスを失った血管・リンパ管は、バリアや水分調整といった機能をなくしたまま、存在していくことになるでしょう。
グリコカリックスが壊れるとむくみやすくなる
グリコカリックスの損傷で心配されることは、むくみやすくなる可能性がある点です。
血管からは水分が外方向に移動しており、出ていく量はグリコカリックスによって調整されています。しかし、グリコカリックスが破壊されて調整機能が働かなくなると、出ていく水分量は増加してしまいます。
結果的に、むくみや腫れといった症状を自覚するようになるでしょう。
リンパ管の損傷によるむくみとしては、リンパ浮腫が挙げられます。リンパ浮腫は、リンパ液の流れが滞ることで、皮下組織に水分やタンパク質がたまり、むくみが生じる病気です。がん治療や外傷・感染・リンパ管系の先天的な異常が原因となります。
がん治療や外傷などで血管やリンパ管のグリコカリックスが破壊されると、血液中の水分が通常よりも外へ漏れ出しやすくなるでしょう。リンパ管が漏れ出した水分を適切に回収する機能を失っていれば、体液は皮下にたまり、慢性的なむくみにつながります。
グリコカリックスの破綻により、水分の、血管におけるバランス調整やリンパ管での回収がうまくいかない状態が続くことは、リンパ浮腫の悪化要因になりかねません。
リンパ浮腫を発症している方が気をつける必要がある合併症の1つに、蜂窩織炎という、細菌感染による炎症があります。
今までも、蜂窩織炎にともなうリンパ管の炎症がリンパ液を運ぶ機能を低下させ、むくみのさらなる悪化を招くことは知られていました。炎症を防ぎ、グリコカリックスを守るという観点でも、感染予防に取り組むことの大切さが証明されたといえるでしょう。
蜂窩織炎を予防するためには、スキンケアや正しい方法での圧迫療法が非常に大切です。
むくみに関する情報は日々更新されている
むくみに関する情報は日々更新されており、今後も新たな知見の発見が続いていくことが期待されます。
これまでは「一度発症したら完治は望めない」とされていたリンパ浮腫についても、新たな治療法・対処法が見つかることもあるかもしれません。ぜひむくみやリンパ浮腫の改善・治療を専門とする機関とつながり、情報をアップデートしていってください。
むくみに関するお悩みはリンパスリム外来へ
むくみに関するお悩みは、1人で抱え込まず、ぜひ一度リンパスリム外来へお聞かせください。
リンパスリム外来では、さまざまな原因で起こったむくみに対し、効果的な弾性ストッキングのご案内や、生活指導を実施しています。
リンパスリム外来を開設している銀座リプロ外科では、リンパ浮腫に対する手術も可能です。ほかの原因によるむくみで、治療が必要な場合は、提携している病院をご紹介いたします。
「どこに相談したら良いかわからない」というつらいむくみの相談窓口として、ぜひリンパスリム外来をお役立てください。
お問い合わせ・ご予約はこちら
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F
この記事の執筆医師

永尾 光一 先生
一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長
医療法人社団マイクロ会 理事長
銀座リプロ外科 院長
昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。形成外科診療科部長を経験する(基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。


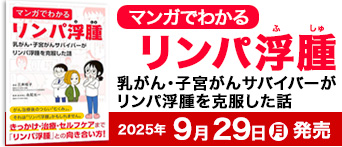
 初診のご予約
初診のご予約 再診のご予約
再診のご予約