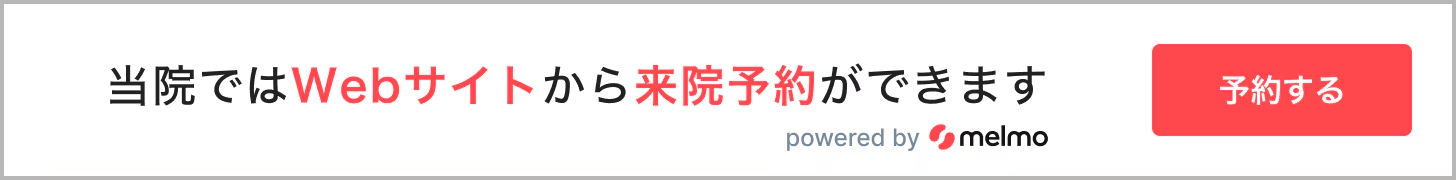「がん治療は終わったけれど、次はリンパ浮腫になるかもしれない」と不安を感じていませんか。普通に生活していても大丈夫かといった、心配は尽きないでしょう。
リンパ浮腫は、早めに適切な治療を行えば、症状の悪化を防げる可能性があります。しかし、放っておくと重症化して治療が難しくなるため、むくみや違和感に気づいたら迷わず専門医に相談することが大切です。
自身の体の状態を確認する方法を知るために、ぜひ本記事を参考にしてください。
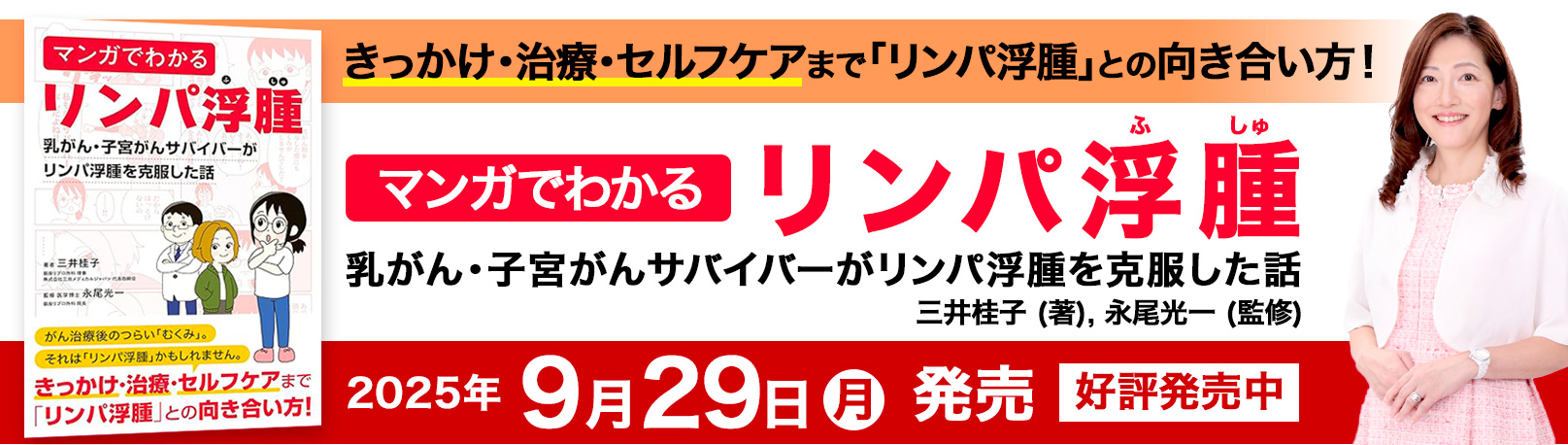
リンパ浮腫を起こしやすいがん治療
リンパ浮腫は、次のようながん治療のあとに生じる場合があります。
・手術
・放射線治療
・抗がん剤治療
がんのあとのリンパ浮腫は、主に治療の影響を受けた部位に発症します。進行の速さや程度には個人差があるため、症状が現れた場合は信頼できる専門医に相談し、早めに対処することが大切です。
手術
がんの手術で大きなリンパ節を切除したりリンパ管が傷ついたりすると、リンパ液の流れが滞り、リンパ浮腫が生じることがあります。がんの進行や転移のために広範囲のリンパ節が切除された場合は、発症のリスクが高まります。
大きなリンパ節を切除することの多いがんは、以下のとおりです。
| がんの種類 | 切除することのあるリンパ節 |
|---|---|
| 乳がん | わきの下のリンパ節 |
|
・子宮体がん ・卵巣がん ・外陰がん ・大腸がん |
脚の付け根のリンパ節 |
|
・子宮がん ・卵巣がん ・大腸がん |
骨盤内のリンパ節 |
リンパ節を切除しなくても、手術時にリンパ管系が損傷を受けると、リンパ液の流れが悪くなり、リンパ浮腫が生じる可能性があります。
放射線治療
リンパ浮腫は、がんに対する放射線治療が原因でも起こります。放射線治療とは、がん細胞が正常な組織に比べて放射線に弱いことを利用した治療法です。
がんの周りのリンパ管に放射線が当たり傷ついた結果、リンパ液の流れが滞ることがリンパ浮腫の原因です。
放射線治療によって、リンパ浮腫を引き起こしやすいがんが存在します。乳がんや婦人科がんでは、リンパ節を切除せず放射線治療のみの場合でも、リンパ浮腫発症の可能性があると報告されています。
放射線を用いたがん治療を受けた方は、リンパ浮腫を発症するかもしれないことを心の片隅に置いておきましょう。
参考:放射線照射は続発性リンパ浮腫発症の危険因子か?|日本リンパ浮腫学会
抗がん剤治療
抗がん剤治療のあとにも、リンパ浮腫が起こるリスクがあります。
本来、抗がん剤治療にともなうむくみはリンパ浮腫とは異なる症状です。薬剤性のむくみは体内に余分な水分が溜まって起こり、利尿剤(水分の排泄を促す薬)で改善が期待できます。抗がん剤治療が終了すると軽快していくことも特徴です。
しかし、抗がん剤によるむくみで体内の循環が悪くなり、リンパ浮腫を生じる患者さんが非常に多く存在します。
同じ手術をした乳がんの患者さんのうち抗がん剤治療をした方は、行なっていない人に比べ、リンパ浮腫の発症割合が高いという報告もあります。
抗がん剤治療のあとにむくみを生じた場合は、注意深いケアや検査の継続が必要です。
参考:乳癌術後続発性リンパ浮腫発症因子についての検討|J-STAGE
リンパ浮腫を放っておくとどうなる?
がん治療後のリンパ浮腫を放っておくと、以下のようなリスクが生じます。
・重症化すると治療が難航する
・感染を起こす危険がある
・象皮症となる可能性がある
リンパ浮腫は、軽症のうちは腕や脚を上げた姿勢をとると軽快することがありますが、重症化予防のためには早めに受診し、治療しましょう。
重症化すると治療が難航する
がんの治療が原因で発症してしまったリンパ浮腫に対処せず重症化した場合は、治療が難しくなる恐れがあります。
重症のリンパ浮腫の症状は、以下のとおりです。
・皮膚が硬く・厚くなる
・皮膚の下に脂肪が沈着する
・組織の成分が変化して元に戻らなくなる
・リンパ液が皮膚から漏れ出す
変性した組織は元に戻らないため、手術で取り除く場合もあります。
リンパ浮腫が重症化すると、関節を動かしにくくなり、歩いたり動いたりすることも困難となります。症状が進行して日常生活に影響を及ぼす前に、早期受診・治療が必要です。症状が進行する前に、早めに専門家へご相談ください。
感染を起こす危険がある
がん治療後のリンパ浮腫を放っておいた場合に考えられるリスクの1つに、感染が起こりやすくなることが挙げられます。
リンパ管系は体液の運搬のほか、免疫機能がうまく働くために必要な器官です。リンパ浮腫になってリンパ管系の働きが悪くなると、腕や脚がむくむだけでなく免疫機能が落ち、小さな傷からでも容易に菌に感染してしまいます。
細菌感染により起こるリンパ浮腫の合併症が、むくんだ腕や脚が赤くはれ、40度近くの熱が出る蜂窩織炎(ほうかしきえん)です。蜂窩織炎は非常に強い炎症反応で、入院を要することもある病気です。
炎症でリンパ管をさらに傷めてしまうので、リンパ浮腫自体が悪化する悪循環に陥る可能性もあります。
象皮症となる可能性がある
重症化して象皮症(ぞうひしょう)を引き起こす恐れがあることも、がん治療後のリンパ浮腫を放置するリスクです。
象皮症は、リンパ浮腫の治療がうまくなされないまま長期間経過した場合に、最終的に陥る状態です。病名は、皮膚が厚くなって乾燥し、くびれのない象のような腕や脚になってしまうことに由来します。
蜂窩織炎を含めた強い炎症反応を長期間繰り返すことで、リンパ管や皮下組織が硬く変性する線維化が起こり、元に戻らなくなって象皮症を生じます。早期にきちんとした治療やケアを行えば予防できる可能性があることからも、リンパ浮腫はすみやかな受診が不可欠です。
がん治療後のリンパ浮腫を早期発見するには
リンパ浮腫を早期発見するために、がん治療後にできることを紹介します。
・むくみやすい場所を知っておく
・日頃から治療部位周辺をチェックする
・腕・脚の太さを測る
リンパ浮腫は、がん治療から数年~10年以上経って発症する場合もあります。しばらくチェックを続けても症状がないからといってやめてしまわず、長い目で経過を見ることが必要です。
むくみやすい場所を知っておく
事前にむくみやすい場所を知っておくと、がん治療後のリンパ浮腫を早期発見できる可能性が高まります。
がんの治療の種類によって異なるむくみやすい場所の例は、以下のとおりです。
| わきの下のリンパ節切除 | 切除したほうのわきの下・腕・胸・背中 |
| 脚の付け根のリンパ節切除 | 切除したほうの脚 |
| 骨盤内のリンパ節切除 | 両方の脚・下腹部・陰部 |
| 放射線治療 | 治療部位の周囲 |
がんのあとのリンパ浮腫は、治療で影響があった部位にのみ出現します。自身がリンパ浮腫を発症する可能性がある治療をしたのかどうか、事前の確認が大切です。
日頃から治療部位周辺をチェックする
リンパ浮腫を早期発見するために、日頃からがんの治療部位周辺をチェックしておきましょう。
リンパ浮腫の多くは、以下のような症状から始まります。
・皮膚のしわが目立たなくなる
・皮膚の上から血管が見えにくくなる
・皮膚が硬くつまみにくくなる
・下着や腕時計・アクセサリーの痕が残る
入浴や着替えの際に、自分の体をチェックする習慣をつけることをおすすめします。左右の腕や脚を比較し、明らかに違いがわかるときはすみやかに専門医を受診しましょう。
腕・脚の太さを測る
がんの治療をした部位周辺の腕・脚の太さを定期的に測ることで、リンパ浮腫の早期発見につながります。
数値を正確に比較できるよう、毎回同じ場所を測ることが大切です。以下の部位を医療機関で用いられている基準に沿って測っておくと、リンパ浮腫の心配がある際に専門医への相談がスムーズにできるでしょう。
| 腕 |
・肘の上10cm ・肘の下5cm ・手首 ・指の付け根 |
| 脚 |
・脚の付け根 ・膝の上10cm ・膝の下5cm ・足首 ・足の指の付け根 |
腕や脚の太さは時間帯でも変化するため、測定は毎日同じくらいの時刻に行なってください。
脚のリンパ浮腫は、がん手術の方法によっては両側に発症することもあります。左右差だけでなく、経過とともに自分の体に変化がないかを細やかにチェックしましょう。
がん治療後のリンパ浮腫予防のポイント
リンパ浮腫を予防するために、がん治療後に意識したいポイントは以下のとおりです。
・リンパ液の流れを良くすることを意識する
・太らないように気を付ける
・体に負担をかけすぎない
やみくもに心配し、ストレスを感じる必要はありません。日常生活のなかで自分の体を気にかける癖をつけ、無理のない範囲でいたわってあげてください。
リンパ液の流れを良くすることを意識する
がん治療後にはリンパ液の流れを良くすることを意識した生活を送り、リンパ浮腫を予防しましょう。
日頃からできるリンパ液の流れを妨げない工夫は、以下のとおりです。
・適度な運動をする
・体を締め付ける衣服や下着・アクセサリーを避ける
・同じ姿勢を長時間続けない
・脚の付け根のリンパ節を取った人は脚を組まない
・脚の付け根や骨盤内のリンパ節を取った場合は正座を避ける
・むくみを感じたら腕や脚を高くして休む
運動の効果を高めたり、リンパ液の貯留を防いだりするために、医療用の弾性スリーブや弾性ストッキングの活用が効果的な場合もあります。自身でのケアに悩んだときは、専門家に相談すると良いでしょう。
太らないように気を付ける
太らないように気を付けることは、がん治療後のリンパ浮腫予防になります。
蓄積した脂肪はリンパ管を圧迫し、リンパ液の流れを妨げます。バランスの取れた食事と適度な運動を心がけ、健康的な体重を維持しましょう。
運動の負荷を調整すれば、手術部位近くの腕や脚のトレーニングをしても、リンパ浮腫の発症原因にはならなかったという研究報告もあります。
運動を生活に取り入れる際は、強度や時間について、専門家にアドバイスをもらうことをおすすめします。無理なく生活習慣を整えながら、心身ともに健やかに過ごしましょう。
参考:乳癌患者における上肢への運動負荷とリンパ浮腫の関係|J-STAGE
体に負担をかけすぎない
リンパ浮腫予防には、がん治療後の体に負担をかけすぎないことも大切です。動きすぎにより血流が増加してリンパ液が増生され、リンパ浮腫の原因となる可能性があります。疲労やストレスも、リンパ浮腫の発症要因の1つです。
仕事や家事で長時間立ったり座ったりしつづけるときは、1~2時間ごとに休憩を入れましょう。スポーツは無理のない範囲で楽しみ、がん治療をした部分に近い腕や脚に過度な負担がかからないよう注意が必要です。
リンパ浮腫予防のためにできる生活の工夫は、以下のとおりです。
・長時間の入浴を避ける
・重いものを持たない
・重作業は家族や地域のサービスを頼る
・長時間同じ姿勢になるバスや電車での旅行は避ける
・気圧の影響を受ける飛行機での移動時には注意する
家族や周囲の人の助けを借り、小さな工夫を取り入れながら、無理のない生活を送りましょう。
がん治療後のリンパ浮腫にお悩みなら当院へ
がん治療後のリンパ浮腫にお悩みなら、当院へご相談ください。
リンパ浮腫は放っておくと症状が進み、重症化して治療が難しくなる病気です。症状が軽いうちに適切なケアを行うことが大切です。
当院にはリンパ浮腫治療の経験が豊富な医師が在籍しており、一人ひとりの状態に合わせたケア方法をご提案します。
腕や脚が少しむくんでいるかもしれないと感じたら、早めの受診をおすすめします。リンパ浮腫と上手に付き合いながら快適な生活を送るために、ぜひ当院へお問い合わせください。
お問い合わせ・ご予約はこちら
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F
この記事の執筆医師

永尾 光一 先生
一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長
医療法人社団マイクロ会 理事長
銀座リプロ外科 院長
昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。形成外科診療科部長を経験する(基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。


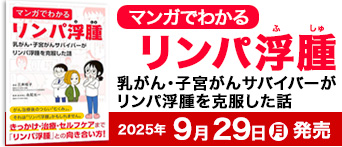
 初診のご予約
初診のご予約 再診のご予約
再診のご予約