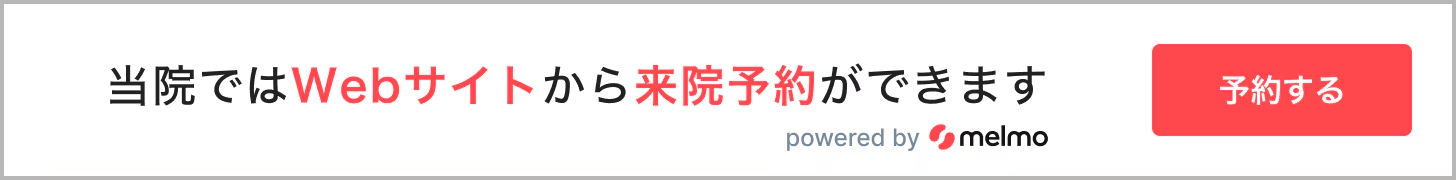男性ブライダルチェックは、性感染症の有無や精子の数・運動率、精巣の異常(エコー検査)などを調べられる方法です。妊活を考えている場合だけでなく、パートナーを守るためにもすべての男性に検査をおすすめします。
本記事では、検査内容や費用を詳しく解説します。パートナーとの将来を見越して、自分の体の状態を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
- 男性不妊・精索静脈瘤にお困りのかたへ
-

男性不妊の40%にある精索静脈瘤は、精巣やその上の精索部(精管、血管、神経、リンパ管などを覆う膜)に静脈瘤(じょうみゃくりゅう・静脈の拡張)が認められる症状のことを指します。一般男性の15%に認められ、男性不妊症患者の40%がその疑いであるとされています。
男性のブライダルチェックとは?
男性のブライダルチェックとは、結婚や妊活をする前に、男性側の健康状態や妊娠にかかわる機能を総合的に確認する検査です。以下のような項目を通して、妊娠に支障がある原因が隠れていないかを事前に確認できます。
- 性感染症の有無(血液・尿検査)
- 精液・精子の状態(精液検査)
- 精巣・陰のう・精管の状態(診察・エコー検査)
検査の結果、子どもをつくるうえで問題が見つかった場合でも、早期に対処できるため影響を最小限にとどめられるでしょう。
ブライダルチェックは、結婚を控えている方だけでなく、独身のうちに自分の体の状態を把握しておきたい男性も受けられます。
感染症や不妊の原因があっても自覚症状がないことが多く、ブライダルチェックを受けて初めて気づく方も少なくありません。妊活や不妊治療をスムーズにスタートするために、女性だけでなく男性も積極的にブライダルチェックを受けることが大切です。
ブライダルチェックと不妊検査の違いは?
男性・女性ともに、ブライダルチェックと不妊検査では、以下のように検査を受ける対象が異なります。
| ブライダルチェック | 結婚・妊活を控えているカップル |
|---|---|
| 不妊検査 | 妊活を始めたのに一定期間妊娠しないカップル |
ブライダルチェックは、今から結婚・妊活を考えている方が性感染症の有無や不妊症のリスクを知っておくための検査です。一方、不妊検査は妊娠に至らない原因をはっきりとさせることが大きな目的です。
男性にもブライダルチェックが必要とされる理由
ブライダルチェックは、以下の理由から男性にも必要とされています。
- 性感染症からパートナーを守ることにつながる
- 子どもをつくるうえで問題がないか確かめられる
- いち早く男性不妊の対策を始められる
「妊娠可能かどうかは女性が検査すれば良い」という考え方は、現在も少なからず残っていますが、不妊の原因の約半分は男性側にもあります。妊活で悩まないためにも、男性も早い段階で自分の体の状態を把握することが大切です。
性感染症からパートナーを守ることにつながる
男性・女性ともにブライダルチェックを行うと、パートナーを性感染症から守れます。
性感染症の多くは初期症状が軽く、感染をまったく自覚しない方もいます。感染に気づかず性行為を行うと、パートナーにうつしてしまい、健康や妊娠へ影響を及ぼすことも少なくありません。
ブライダルチェックで性感染症の有無を調べると、必要に応じて早期に治療が受けられます。事前に検査しておくことで、結婚後にトラブルが起こるリスクを減らせるでしょう。
子どもをつくるうえで問題がないか確かめられる
ブライダルチェックでは、不妊や胎児への異常のリスクが男性にないかを確認可能です。
精子の数や運動率・正常形態率などの精液所見が悪いと、受精や着床に至る確率が下がる可能性があります。さらに、精子の質によっては以下のリスクを高めることにもつながります。
- 流産・死産する確率
- 早産になる確率
- 低出生体重児や先天性異常(奇形)になる確率
精子の数が少ない、運動率が低いなどの異常があった場合は、生活習慣の改善や早期の治療開始につなげられます。超音波検査で精索静脈瘤が見つかった場合は、手術によって精液所見の改善が望めるでしょう。
結婚後、思ったように妊娠が叶わずに焦って検査を受けるより、余裕のある時期に体の状態を確認しておくほうが、計画的に妊活を進められます。
いち早く男性不妊の対策を始められる
いち早く男性不妊の対策を始められることも、ブライダルチェックが必要といわれる理由です。
男性不妊の原因のなかには、精索静脈瘤といった、早期に治療を行わないと精液所見が次第に悪化する病気があります。妊娠の可能性を下げないためには、早期の検査と治療が欠かせません。
ブライダルチェックは、将来の妊活に必要な治療を結婚前から検討できるきっかけになります。早く対策することで、タイミングを逃さず、計画的な家族づくりが可能です。
ブライダルチェックを特に受けたほうが良い男性とは
次のような男性は、ブライダルチェックを特に受けたほうが良いといえます。
- 性感染症にかかっているか心配である
- 精巣・陰のうの形が悪い・精巣の病気になったことがある
- 年齢が35歳以上である
- 喫煙している
基本的に、ブライダルチェックは結婚や妊活を考えているすべての男性におすすめですが、特徴に当てはまる方は特に前向きに検討しましょう。
性感染症にかかっているか心配である
性感染症の心配がある方は、積極的にブライダルチェックを受けてください。性感染症とは、性行為でうつる病気の総称で、性器クラミジアや淋菌感染症・エイズ(HIV)などが代表的です。
一般的な健康診断では検査できないため、ブライダルチェックでの確認が大切です。
男性は性感染症を患っても自覚症状が出ないことが多く、気づかない場合もあります。治療せず放置すると、精液の状態に影響してしまうでしょう。
パートナーに性感染症がうつり、卵管や子宮に炎症が起こることで、女性側の不妊の原因になりかねません。男女ともに不妊の原因があると、妊娠の可能性はさらに低くなってしまいます。
結婚生活に不安を残さないためにも、ブライダルチェックで早期に検査し、陽性であれば治療してください。自分とパートナー双方の健康を守る意味でも、結婚前の性感染症検査は非常に有効です。
精巣・陰のうの形が悪い・精巣の病気になったことがある
ブライダルチェックは、以下の男性に特に推奨されます。
- 停留精巣の手術を受けた
- 鼠径ヘルニアの手術を受けた
- おたふく風邪にかかり精巣が腫れた
- 抗がん剤治療や放射線治療を受けた
- 精索静脈瘤を指摘された(または陰のうの左右差がある)
精巣や陰のうにかかわる病気は、精巣機能が低下したり、精管が傷つき精子が出にくくなったりする原因につながります。自覚症状はなくても精子の質が低下しているケースもあるため、ブライダルチェックで検査することが大切です。
年齢が35歳以上である
35歳以上の男性は精液所見や性欲が低下する傾向にあるため、ブライダルチェックを受けることをおすすめします。男性の生殖機能は30代から少しずつ低下するといわれており、35歳以降は以下のような数値に顕著に表れます。
- DNAが破損した精子の数
- 精子の数・濃度
- 精子の運動率
精液所見が悪くなると、妊娠の成立が難しくなりかねません。受精卵の分割を進める力は、35歳を境に急激に下がるという報告もあります。さらに精索静脈瘤があると悪化が加速します。
精液所見の悪化による流産や胎児・子どもの発達への影響も指摘されています。35歳を過ぎたら、自分の体の状態を知るためにもブライダルチェックを活用してください。
喫煙している
喫煙の習慣がある男性はブライダルチェックを受け、不妊につながる要素がないか調べましょう。喫煙は、精子の数の低下や、形態異常の増加に関連することがわかっています。
タバコに含まれる多くの有害物質は、精子のDNAを損傷させ、正常な妊娠を阻害する要因です。電子タバコにも有害物質は含まれているため、紙タバコと同様に不妊のリスクを高めます。
タバコは、主流煙より有害な副流煙を発生させます。副流煙の害を受けているパートナーは、不妊の原因になる卵子の染色体異常を起こす確率が上昇するため注意が必要です。
自身だけでなくパートナーの健康を守れるよう、禁煙するとともに、ブライダルチェックを積極的に受けましょう。
男性ブライダルチェックの検査内容1|感染症
男性ブライダルチェックで行われる、以下の2つの感染症検査について詳しく解説します。
- 性感染症検査
- 風しん抗体検査
検査結果に応じて適切な対処をすることで、妊娠・出産時のリスクを低下させられるケースもあるため、事前にしっかりと確認してください。
性感染症検査
ブライダルチェックで検査される性感染症と、感染した場合に妊娠・出産に与えるリスクは、以下のとおりです。
| 性感染症 | 検査方法 | 感染によるリスク |
|---|---|---|
| 淋菌感染症 | 尿検査 |
・男女ともに不妊の原因になる ・流産・早産・前期破水のリスクが上昇する ・赤ちゃんが結膜炎になる可能性がある |
| 性器クラミジア | 尿検査 |
・男女ともに不妊の原因になる ・流産・早産のリスクが上昇する ・赤ちゃんが肺炎や結膜炎になる可能性がある |
| 梅毒 | 血液検査 |
・胎盤を通じて母子感染する ・死産・早産のリスクが上昇する ・出生児に発疹・骨の異常・目の炎症・難聴のリスクが生じる |
| エイズ(HIV) | 血液検査 |
・適切な対処をしないと15~30%が母子感染する ・適切な対処をすれば母子感染率は1%未満である |
| 性器ヘルペス | 血液検査 |
・新生児ヘルペスを発症する可能性がある ・新生児ヘルペスの全身型と中枢神経型では、後遺症や死亡のリスクがある |
| HPV感染症 | HPV DNA検査 |
・子宮頸がんや陰茎がんといったがんの発症リスクを高める ・胎児ののどにイボができる |
| B型肝炎 | 血液検査 |
・赤ちゃんに黄疸や発育不良が見られる可能性がある ・赤ちゃんが肝臓の病気になるリスクが高まる |
| C型肝炎 | 血液検査 | ・精巣に炎症を起こし不妊の原因となる |
一般的に女性は妊婦検診で性感染症の検査を受けますが、男性は機会が少なくなりがちです。パートナーにうつしてしまう前に、確認しましょう。
風しん抗体検査
風しんに対する抗体の有無は、男性のブライダルチェックに欠かせない検査の1つです。
風しんとは、ウイルスによって引き起こされる急性の発疹性感染症です。妊娠初期の妊婦が風しんにかかると、先天性風疹症候群を患った子どもが生まれる可能性が高まります。先天性風疹症候群とは、先天性心疾患や難聴・白内障などを特徴とした病気です。
風しんは飛沫感染で広がるため、妊娠している方だけでなく、周囲の人にもかからないよう注意してください。
風しんウイルスに対する免疫は、ワクチン接種を2回することで95%程度獲得できるといわれています。しかし、風しん予防接種を受けた回数は、生まれた年代によって以下のように異なります。
| 男性の生まれた年代 | 接種回数 |
|---|---|
| 平成2年4月2日以降 | 2回 |
| 昭和54年4月2日~平成2年4月1日 | 1回 |
| 昭和54年4月1日以前 | 0回 |
2016年度の感染症流行予測調査によると、30代後半~50代の男性の5人に1人、20~30代前半では10人に1人が風しんの免疫を持っていません。ブライダルチェックで「風しんの抗体がない」と診断された方は、妊活前に予防接種を受けましょう。
男性ブライダルチェックの検査内容2|精液・精子の状態
男性のブライダルチェックで行う精液検査では、精液や精子の状態を調べ、妊娠が望めるかどうかを調べます。精液検査で調べられる主な項目と自然妊娠が期待できる下限基準値は、以下のとおりです。
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 精液量 | 1.4ml以上 |
| 精子濃度 | 1600万/ml以上 |
| 精子の運動率 | 42%以上 |
| 精子の正常形態率 | 4%以上 |
| pH | 7.0~8.0 |
精液の状態は、採取場所・禁欲期間・採精からの時間・体調などの条件によって容易に変化します。特に、自宅で採精した場合は、さまざまな影響を受け、精液所見が悪くなる傾向があります。
精液検査の際は、3日間の禁欲後、検査する病院内で採取することがおすすめです。院内採取ができない場合は、体温くらいの温度を保ちながら、検査する医療機関まで可能な限り30分以内に運びましょう。
男性ブライダルチェックの検査内容3|超音波(エコー)検査
ブライダルチェックで超音波検査を受けると、男性不妊につながる原因を特定できるケースがあります。超音波検査では、体の表面にプローブと呼ばれる器械をあて、以下の内容を確認します。
- 精巣・陰のうの状態
- 精索静脈瘤の有無
- 精子の通り道の異常
- 血流
- 腫瘍や結石の有無
検査を通して、精液検査における問題の原因が、精巣や陰のうにないかを視覚的に確認可能です。
精索静脈瘤だけでなく、精巣腫瘍や陰嚢水腫といった病気も発見できます。男性のブライダルチェックにおける超音波検査は、患者さんにとって負担が少ないうえ、多くのことがわかる重要な検査です。
男性ブライダルチェックの流れ
男性が行うブライダルチェックの流れは、以下のとおりです。
- 予約
- 受付・問診
- 血液・尿検査
- 精液検査・陰のうの診察と超音波検査
- 結果の説明
ブライダルチェックは、泌尿器科や不妊専門クリニックで受けられます。2回通院し、初回の受診では受付と問診のあと、採血・採尿を行うことが一般的です。
2回目の受診時には、精液検査と陰のうの診察・超音波検査を実施します。持参またはクリニック内で採取した精液をすぐに検査してもらい、血液・尿検査の結果とともに、医師から説明を受けてください。精索静脈瘤が見つかった場合は手術が検討されます。
男性ブライダルチェックの費用は?
男性ブライダルチェックの費用に関して、公的保険適用の有無とおおよその金額をあらかじめ確認しておきましょう。
各泌尿器科や不妊専門クリニックのプランを比較する際は、検査項目と費用のバランスを考えることが大切です。保険診療の有無や、費用の目安を解説します。
公的保険は適用される?
ブライダルチェックは健康診断と同じ扱いのため、公的保険は適用されません。クリニックが検査の金額を独自に決められる自由診療にあたり、全額自己負担となります。
ただし、不妊検査を受けた場合に助成金を申請できる自治体もあります。以下は、関東の自治体公式サイトで確認できる、助成金制度の一例です。
| 自治体 | 助成される内容 | 助成金額 |
|---|---|---|
| 東京都 | 保険医療機関で行なった不妊検査・一般不妊治療に要した費用 | 5万円まで |
| 埼玉県 | 不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査費用 | 35歳以上の方は2万円まで |
都道府県だけでなく、市区町村単位で助成している自治体もあります。ブライダルチェックで不妊の可能性が高いとわかった場合は、追加で受ける検査が助成金の対象にならないか調べてみましょう。
どのくらいの費用がかかる?
男性のブライダルチェックにかかる費用は、およそ3~5万円です。ただし、自由診療扱いのため、同じ検査内容でも泌尿器科・クリニックによって費用は大きく異なります。ブライダルチェックに含まれる検査項目も、医療機関によってさまざまです。
検査費用は、医療機関の設備や医師の熟練度によって差が生じることもあります。
クリニックを選ぶ際は、費用面だけではなく検査内容やクリニックの専門性にも注意を払うと良いでしょう。
男性不妊が疑われる場合の追加検査
ブライダルチェックの結果から男性不妊が疑われる場合は、以下の検査を追加で行います。
- ホルモン・ミネラル血液検査
- 染色体・遺伝子検査
- 精子精密検査
原因を明らかにすることで、適切な治療方針を立てやすくなり、妊活の成功率も高まります。
ホルモン・ミネラル血液検査
採血によるホルモン・ミネラル血液検査は、ブライダルチェックで不妊の疑いがある男性にすすめられる検査です。
ホルモン・ミネラル血液検査では、採血をして以下の項目を調べ、精巣の働きや精子をつくる機能に異常がないかを確認します。
| ホルモン |
・卵胞刺激ホルモン(FSH) ・黄体形成ホルモン(LH) ・プロラクチンテストステロン(男性ホルモン) ・エストラジオール(女性ホルモン) |
|---|---|
| ミネラル・ビタミン |
・ビタミンD ・亜鉛 ・カルニチン ・銅 |
ホルモンの数値が低いと、低ゴナドトロピン性性腺機能低下症のような内分泌系の病気が疑われます。適切な治療によってホルモンの値が正常に近づけば、精液所見の改善が期待できるでしょう。
ミネラルやビタミンは、精子の成熟・運動性・DNA保護を助けるともいわれる栄養素で、不足が悪影響を及ぼしている可能性もあります。医療機関によっては、サプリメントの摂取といった薬物療法が提案されます。
染色体・遺伝子検査
ブライダルチェックで精液所見が悪かった場合は、必要に応じて染色体や遺伝子の検査を検討してください。
男性不妊を引き起こす染色体や遺伝子の異常の一例として、以下の2つを紹介します。
| 遺伝子異常の病気 | 症状 |
|---|---|
| クラインフェルター症候群 |
・停留精巣や精巣容積の低下 ・無精子症 |
| Y染色体微小欠失 |
・精子数や運動性、形態の異常 ・乏精子症 ・無精子症 |
遺伝子レベルでの異常が明らかになった場合でも、体外受精・顕微授精といった高度生殖医療の選択で妊娠が目指せるケースもあります。原因がわからないまま不妊治療を進めるよりも、適切な検査を受けて情報を得ることが重要です。
精子精密検査
男性ブライダルチェックでの精液所見に問題がないにもかかわらず、なかなか妊娠に至らない場合は、精子精密検査を受けましょう。
以下のような精子精密検査により、一般の精液検査より詳しく精子の質を調べられます。
| 検査名 | 検査内容 |
|---|---|
| DFI検査 | 精子のDNA損傷率(断片化率) |
| ORP検査 | 精子のDNAにダメージを与える酸化ストレスの程度 |
一般の精液検査では異常が認められなくても、精子精密検査を受けると精子のDNAの損傷がわかるケースもあります。精子のDNA損傷は、男性不妊や流産率の上昇といった悪影響を及ぼす可能性があるため、精密検査で詳しく調べることは非常に大切です。
精子の酸化ストレスやDNA損傷は、精索静脈瘤によって引き起こされるケースもあります。精索静脈瘤の手術によって精巣の環境が良くなれば、精子の状態の改善が期待できます。
男性不妊の4割は精索静脈瘤
男性不妊の患者さんの4割は、精索静脈瘤が原因といわれています。精索静脈瘤は成人男性の約15%に見られることから、決して珍しい病気ではありません。精索静脈瘤とは、精巣から心臓へ戻る血管で血液の逆流が起こり、陰のうや精索部分の静脈が拡張する病気です。
血液が逆流すると、精巣温度の上昇や血流の悪化を招き、以下の症状が見られます。
- 陰のうの痛みや違和感
- 陰のうサイズの左右差といった外見的変化
- 精巣の萎縮と機能低下
精索静脈瘤は精巣の機能に悪影響を及ぼすため、精子の数や運動率の低下、精子DNA損傷の原因になります。男性ホルモンの低下も引き起こし、性欲の減退や勃起障害につながると、性交渉に問題が生じる恐れがあり注意が必要です。
精索静脈瘤はあまり進行していない段階でも、視診や触診、超音波検査で簡単に診断が可能です。症状が軽いうちに治療することで、精液所見の改善が見込めるでしょう。
当院で行う精索静脈瘤治療
当院では、独自の手術法である「日帰り顕微鏡下精索静脈瘤手術・ナガオメソッド」により精索静脈瘤治療を行います。
日帰り顕微鏡下精索静脈瘤手術・ナガオメソッドは、逆流により拡張した静脈だけを結紮(けっさつ)・切離するため、一般的な手術法と異なり、問題のない血管・リンパ管・神経はすべて残せる点がメリットです。手術後の精液所見は87%の方が改善し、術後の痛みはほとんどありません。
高度な技術を持った医師が、内精逆流静脈だけでなく外陰部(外精)逆流静脈も結紮・切離し、再発率を0.1%にまで抑えます。外陰部(外精)逆流静脈を結紮・切離しない他の術式では再発率が5%高くなります(ヨーロッパ泌尿器科ガイドライン2025)。
合併症のリスクもほとんどないため、患者さんの身体的負担が少なく済むでしょう。
男性ブライダルチェック後のご相談は当院へ
男性ブライダルチェックで精液所見が悪く、精索静脈瘤が疑われる際は、当院へご相談ください。当院では、精索静脈瘤の検査や手術を含む、男性不妊の治療を実施しています。
当院独自の「日帰り顕微鏡下精索静脈瘤手術・ナガオメソッド」は、再発率が0.1%と低く、精液所見の改善率が87%と高いことが特徴です。局所麻酔を使う手術は1時間ほどで終わるうえ、日帰りが可能です。
精索静脈瘤は進行性の疾患で、放っておくと精巣の機能や精子の状態が次第に悪化していきます。早期治療のために信頼できる医療機関をお探しの方は、ぜひ当院にお問い合わせください。
お問い合わせ・ご予約はこちら
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F
この記事の執筆医師

永尾 光一 先生
一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長
医療法人社団マイクロ会 理事長
銀座リプロ外科 院長
昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。その後、東邦大学で泌尿器科学を専攻し、形成外科・泌尿器科両方の診療科部長を経験する(2つの基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。泌尿器科医の枠を超えた細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。


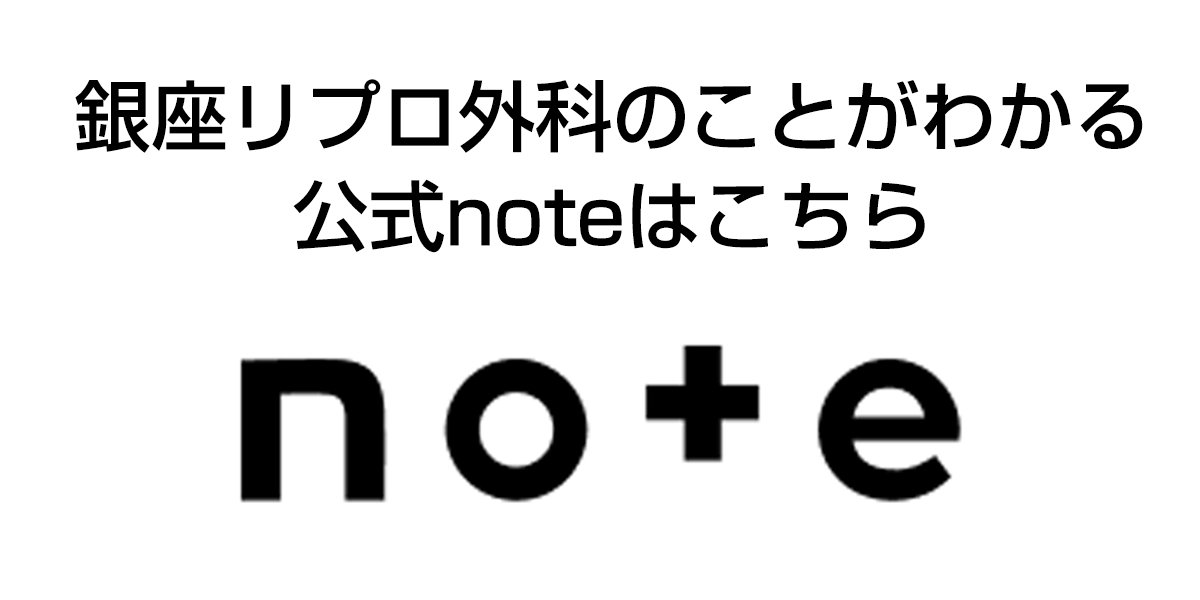
 初診のご予約
初診のご予約 再診のご予約
再診のご予約