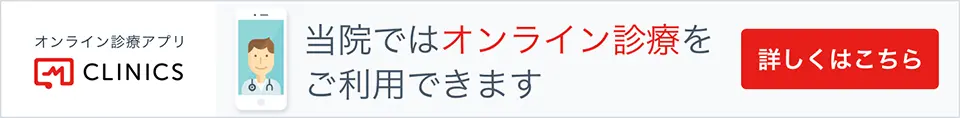タイミング法から体外受精へ、不妊治療のステップアップをお考えではないでしょうか。
体外受精は、体の外へ卵子と精子を取り出し、受精させる方法です。卵子と精子を直接出会わせるため、タイミング法と比べて受精しやすいというメリットがあります。
ただし、体外受精は必ず成功する方法ではありません。何回試行しても妊娠できなかったり、費用が高額になったりする可能性がある点に注意しましょう。
体外受精の妊娠成功率を上げるには、精子の質を高める必要があります。
本記事では、体外受精の手順・スケジュール・妊娠成功率や、顕微授精との違いについて紹介します。
- 男性不妊・精索静脈瘤にお困りのかたへ
-

男性不妊の40%にある精索静脈瘤は、精巣やその上の精索部(精管、血管、神経、リンパ管などを覆う膜)に静脈瘤(じょうみゃくりゅう・静脈の拡張)が認められる症状のことを指します。一般男性の15%に認められ、男性不妊症患者の40%がその疑いであるとされています。
体外受精とは?
体外受精とは、排卵直前の卵子を取り出し、体外で精子と受精させる方法です。自然な妊娠が難しい夫婦の受精率を高められる一方、デメリットも存在します。体外受精が適するケースも紹介するため、受診するか悩んでいる場合は参考にしてください。
体外受精の方法
体外受精とは、不妊治療の1つで、体の外で卵子と精子を受精させて胚(はい)を作る方法です。
シャーレ内で卵子に精子をふりかけて受精を促したあと、数日間培養して胚を育てます。培養したなかから状態が良好な胚を選択し、子宮へ戻します。
体外受精が成功するためには、体内へ移植された胚が子宮内膜にしっかりと着床することが大切です。着床とは、胚が子宮内膜に根を下ろすようにくっつき、成長を始めることです。体外受精では、胚が着床しやすいよう、子宮内膜の状態を整える治療も行われます。
着床後、赤ちゃんを包む膜である胎嚢(たいのう)や心拍が確認されれば、妊娠成立だと判断されます。
体外受精のメリット
体外受精のメリットは、タイミング法や人工授精に比べて受精率が高い点や、卵子への負担が少ない点です。
年齢を重ねた女性は、妊娠率を上げるためにできる限り早く妊活に取り組むことが望ましく、タイミング法よりも体外受精のほうが時間的に効率が良いといえます。
また、体外受精は精子自身の力で受精させるため、卵子が変性したり傷ついたりするリスクを低減できます。
卵管が癒着して閉塞している場合や、多嚢胞性卵巣症候群のように、卵巣に問題がある母体でも、体外受精は可能です。体内に精子を攻撃する抗精子抗体を持っている女性にも有効な手段です。
体外受精のデトックス
体外受精には、以下のようなデメリットもあります。
・通院回数が増える
・卵巣刺激や採卵の際に女性に負担がかかる
・経済的な負担を要する
体外受精では、排卵を誘発させる薬が処方されるため、通院しなければなりません。通院回数が増えると、費用が高額になる点にも注意が必要です。
排卵誘発剤で得られた成熟卵の摘出(採卵)では、針を刺したときに痛みがともなうため、多くの場合で麻酔が使用されます。女性には、排卵誘発剤や麻酔の副作用をはじめとするリスクがともないます。
受精しても、必ずしも着床するわけではありません。着床しない場合は、体外受精が繰り返し行われることにより、経済面での負担が高額となります。
高額な不妊治療の費用を共働きで負担している夫婦も大勢います。しかし、女性は仕事を休んで治療を受けなくてはならないケースが大半なので、職場の上司や同僚からの理解も必要です。
体外受精が適するケース
体外受精は、タイミング法や人工授精を一定期間繰り返し行なってもうまくいかない場合や、卵管障害・排卵障害による不妊の方に適します。卵巣機能が低下して妊娠しにくいと思われる母体にも選択される方法の1つです。
体外受精は、女性側だけでなく男性側が不妊の原因を抱えるケースでも有用です。精子の数が極端に少なかったり、運動率が低かったりする場合は、体外受精へのステップアップを勧められることがあります。
自分の精液や精子の状態に体外受精が必要かどうかを早めに医師へ相談し、検査を受けることをおすすめします。ただし、男性不妊の場合は、泌尿器科で精索静脈瘤と診断されれば手術で精液が改善し自然妊娠の可能性があります。
体外受精とほかの不妊治療方法との違い
体外受精とほかの不妊治療における受精方法の違いは、以下の表のとおりです。
| 受精方法 | |
|---|---|
| 人工授精 | 精子を子宮内に注入して自然受精させる |
| 体外受精 | 精子と卵子をシャーレで自然受精させる |
| 顕微授精 | 精子1個を卵子に注入して人為的に受精させる |
人工授精・顕微授精と体外受精の違いについて、詳しく解説します。不妊治療のステップアップを考えている場合は、ぜひ参考にしてください。
人工授精と体外受精の違い
人工授精と体外受精の違いは、受精の起こる場所が体内か体外かです。不妊治療では、人工授精を先に検討する方が多いでしょう。
人工授精では、処理された精子を排卵の時期に管で子宮に注入することで、体内での受精を期待します。一方、体外受精は、シャーレ内で体から取り出した卵子に精子をふりかけたあと、培養して受精を起こします。
精子が自力で卵子に入っていくことで受精が起こる点は共通していますが、人工授精のほうが自然妊娠に近く、女性への負担が少ない方法です。体外受精は高度な治療法であり妊娠率の高さが強みで、人工授精と比べて高額な費用がかかります。
顕微授精と体外受精の違い
顕微授精が体外受精と異なる点は、卵子に人為的に精子を注入することです。体外受精はシャーレの中で自然な受精を待ちますが、顕微授精では顕微鏡を使い、卵子の中に1つの精子を注入します。
1個の精子がいれば顕微授精が可能なため、体外受精をするには精子数が足りない乏精子症でも受精できます。ただし、顕微授精は卵子に針を刺すため、傷つけてしまうリスクがある点に注意が必要です。
精子が少ない場合は、あらかじめ精巣から精子を取り出し、凍結保存しておくことがあります。顕微授精・体外受精はともに、凍結保存した精子を使って行えます。
体外受精の手順とスケジュール
体外受精の具体的な手順は、以下のとおりです。
1.排卵誘発
2.採卵
3.採精
4.受精
5.胚培養
6.胚移植
7.黄体ホルモン補充
8.妊娠判定
月経3日目頃から排卵誘発を始め、胚移植後2〜3週間程度で妊娠判定を行います。1回の体外受精で妊娠が叶うまでには、約1〜2ヵ月かかります。
1.排卵誘発
排卵誘発は、体外受精の最初のステップです。排卵誘発剤を用いて卵巣を刺激することで卵胞(卵子)を発育させ、排卵を促します。排卵障害のある場合だけでなく、正常周期で排卵が起こる方でも妊娠確率を上げるために行われる方法です。
排卵誘発(卵巣刺激)は下記3つの方法を用いることが多く、個々の卵巣の状態や希望に合わせて選択されます。
・無刺激法(完全自然周期)
・低刺激法(クロミッド法)
・高刺激法
無刺激法は、排卵誘発剤を使用しない方法です。身体への負担が少なく、卵子を凍結しないため費用が抑えられます。ただし、ほかの方法に比べると採卵できる数が少なく、胚移植をキャンセルしなければならない月が出てくる可能性もあります。
低刺激法は、排卵を誘発する薬であるクロミッドを内服したり、卵胞の発育を促すホルモン製剤であるHMGを注射したりする方法です。採卵数は完全自然周期よりも多くなりやすく、凍結保存を行うこともあります。
高刺激法は、排卵誘発剤の注射を連日打ち、卵巣を刺激する方法で、多くの卵子を採取できます。注射の回数が多くなるため、費用が高く副作用が起こりやすい点に注意が必要です。
2.採卵
排卵誘発後の体外受精のステップは、採卵です。
経腟超音波を用いてモニターを見ながら膣に細い針を刺し、排卵前の卵胞から卵子を吸引して採卵します。無麻酔でも採卵は可能ですが、針を刺すと痛いので、多くのケースでは座薬・局所麻酔・静脈麻酔などが用いられます。
採卵日は、一般的に月経開始後10〜14日目頃です。しかし、卵子の成熟度合いの影響を受けて変わり、受診する医療機関の治療方針によっても決め方が異なります。
3.採精
男性は、採卵日と同日に精子の採取を行う必要があることも忘れてはいけません。体外受精しやすい精子の濃度や運動率になるよう、採精のおよそ2〜3日前からの禁欲を推奨します。
精子は、採卵当日に自宅で採取した精液を持参するか、病院内で採精します。自宅で採精する場合は、精子の質が落ちないよう体温と同じ程度に保温して運搬し、早め(30分以内)に病院へ持ち込むことが大切です。
「自宅から病院までが遠い」「スケジュールが合わない」という方は、精子を凍結保存しておく方法もあります。しかし、凍結保存した精子は運動率が低下し、体外受精を行えない場合もあるため、当日の採精が望ましいでしょう。
4.受精
卵子と精子の採取後の工程は受精です。体外受精では、精液を洗浄・濃縮したあと、良好な運動精子を回収してシャーレの上で卵子と自然に出会わせます。精子に問題がない場合は、放置するだけで自然と受精できるでしょう。
体外受精では精液の処理が行われるものの、精子に受精できる力があることは非常に重要です。精子の運動率が低い場合は、体外受精の成功率が下がる恐れがあります。
精子の質を下げる(精子のDNAダメージなど)精索静脈瘤のような要因が自身にないか、事前に泌尿器科で検査することが大切です。
5.胚培養
精子と卵子を受精させたあとの過程が、母体に戻せるよう適切な環境で受精卵を成長させる胚培養です。
体外受精において、受精卵はグルコースや乳酸などの栄養素を含む専用の培養液で培養されます。インキュベーターという温度・湿度・ガス濃度などを一定に保てる機械で子宮内と同じような環境を作り、受精卵の発育を助けます。
受精卵がインキュベーターの中で細胞分裂を起こし、成長した姿が胚です。胚を子宮内に移植できる状態になるまで発育させるには、3日程度の培養期間が必要です。
6.胚移植
胚を着床できる状態である胚盤胞(はいばんほう)まで成長させたら、良好な個体を柔らかいカテーテルで子宮内に移植します。
移植できる胚の数は、双子や三つ子などの多胎妊娠を防ぐために原則1個です。ただし、女性の年齢が35歳を過ぎていたり、2回以上続けて不成立であったりする場合は、最大3個までの胚移植が許容されます。
参考:多胎妊娠防止のための移植胚数ガイドライン|一般社団法人日本生殖医学会
胚移植には、受精後2~3日を経過してから行われる初期胚移植と、5~6日培養した胚を使う胚盤胞移植があります。多くの病院で妊娠率が高いと報告されている方法は、胚盤胞移植です。
胚移植の着床率を高めるために、「アシステッド・ハッチング」という技術が用いられる場合もあります。
アシステッド・ハッチングは、胚を包む透明帯という膜を薄くしたり開孔したりすることで、着床しやすくなるようサポートする方法です。着床の第一歩は胚が透明帯から出ることであり、膜が厚く硬いと起こりにくくなります。
7.黄体ホルモン補充
体外受精では、着床率を高めるために黄体ホルモン(プロゲステロン)が補充されるケースがあります。
黄体ホルモンとは、排卵後のタイミングで分泌量が多くなり、妊娠しやすいよう子宮内膜を成熟させるホルモンです。補充期間中は、注射や薬の服用・膣座薬などを毎日行う必要があります。
黄体ホルモン補充の治療中に、皮膚の発疹や吐き気といった副作用が起こる方もいます。妊娠判定が待ち遠しい時期ですが、パートナーの体調を気にかけることを忘れないでください。
8.妊娠判定
体外受精の妊娠は、血液検査や尿検査で判定されます。hCGと呼ばれるホルモンの分泌量を測定し、一定基準以上の値が出れば妊娠成功です。
妊娠判定を行う日の目安は、胚移植の種類によって異なります。初期胚移植では移植日から約14〜21日後、胚盤胞移植ではおよそ7〜10日後です。妊娠していても検査日が早すぎるとhCG測定値が低く、陽性判定が出ないため、決められた日にちを待ちましょう。
妊娠判定後、エコー検査で胎嚢や心拍が確認できれば、体外受精のプロセスは完了です。
体外受精による妊娠の成功率
体外受精による妊娠成功率は、2022年に日本産科婦人科学会から報告されており、凍結していない新鮮胚を用いた胚移植では24.6%です。ただし、妊娠率は奥様の年齢や医療機関ごとに差があります。
参考:2022年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績|日本産科婦人科学会
一般的に、年齢が高いほど妊娠率は低下します。胚移植あたりの妊娠成功率は、女性が20代の夫婦で40〜50%程度と報告されていますが、30代後半の場合は20〜40数%です。
赤ちゃんを望むカップルは、できる限り早く行動したほうが良いことを認識しておきましょう。
体外受精の成功率を上げるために男性不妊の検査を
体外受精の成功率を上げるためには、卵子と同時に、精子の質を高めることも大切です。DNA・染色体が損傷している精子では妊娠率が低下します。
精液検査をし、濃度・運動率・正常精子形態率などの値が悪い場合は、泌尿器科の受診がおすすめです。精索静脈瘤のような精子の質を下げる疾患が見つかった方は、治療してから体外受精をしましょう。
精索静脈瘤は、一般男性の15%ほど、男性不妊の方の約40%に見られる病気です。精管・血管などが束になった精索内の静脈が広がって瘤(こぶ)ができ、精巣機能の低下を引き起こします。
症状を自覚しにくく、精液検査で精子の数や運動率の低下を指摘されて初めて病気に気づく患者さんも少なくありません。精索静脈瘤は治療でき、手術後3~6ヵ月程度で精液所見が改善する方が大勢います。
男性側の不妊原因を治療することにより、妊娠率・出産率がアップし、流産・奇形の確率を低下させられる可能性があります。
男性不妊に関するお悩みは当院へ
「自分に不妊の原因があるのではないか」と不安な男性は、体外受精を検討する前にぜひ一度当院へご相談ください。
当院は、男性不妊の治療に特化したクリニックです。精索静脈瘤に対し、精液検査の結果を根本的に改善するための「日帰り顕微鏡下精索静脈瘤手術・ナガオメソッド」を行なっています。
鼠径部あたりを数センチ切開し、顕微鏡で拡大しながら血管・リンパ管・神経などを1本1本確認します。逆流に関連する静脈だけを1本ずつ丁寧に糸でしばり切離するので、合併症のリスクが低い方法です。
内精逆流静脈だけでなく外陰部逆流静脈も結紮・切離することから、再発率を下げられます。
当院は、患者さんが安心して過ごせるよう、プライバシーへの配慮を心がけています。診察室は個室なので、「悩みを人に聞かれるのではないか」と気にする必要はありません。完全予約制で、待合室に大人数が集まることはなく、リラックスしてお過ごしいただけます。
男性不妊にお悩みの方は、ぜひ当院へお問い合わせください。
お問い合わせ・ご予約はこちら
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F
この記事の執筆医師

永尾 光一 先生
東邦大学 医学部教授(泌尿器科学講座)
東邦大学医療センター大森病院 リプロダクションセンター
東邦大学医療センター大森病院 尿路再建(泌尿器科・形成外科)センター長
昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。その後、東邦大学で泌尿器科学を専攻し、形成外科・泌尿器科両方の診療科部長を経験する(2つの基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。泌尿器科医の枠を超えた細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。
所属医療機関



 初診のご予約
初診のご予約 再診のご予約
再診のご予約